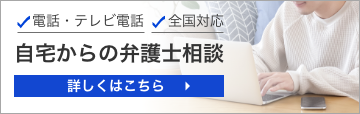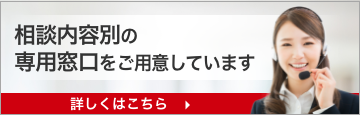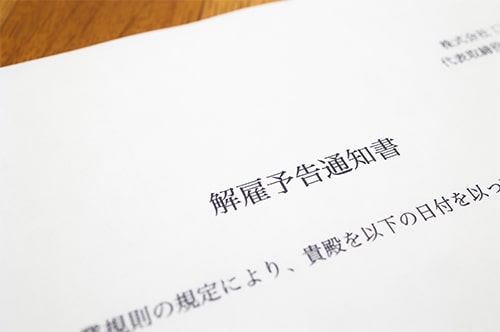中小企業も対象! 月60時間以上の残業代は賃金の1.5倍に
- 労働問題
- 残業代
- 1.5倍

令和3年6月時点における横浜市内の事業所数は約7万3000件に上り、そのうち99.5%以上が中小企業に該当します。
労働者が月60時間超の残業をしたときは、基礎賃金に50%以上の割増賃金を加えた残業代(基礎賃金の1.5倍)を支払わなければなりません。60時間超の残業に対する50%以上の割増率は、当初は大企業のみが対象とされていましたが、令和5年4月から中小企業にも適用されることになりました。
残業代計算を間違えると労働者から未払い残業代の支払いを求める労働審判の申し立てや訴訟提起をされるリスクがあるため、しっかりと対応していく必要があります。今回は、中小企業も適用対象となる、月60時間以上の残業に対する50%以上の割増賃金について、ベリーベスト法律事務所 横浜オフィスの弁護士が詳しく解説します。
1、月60時間超の残業には基礎賃金の1.5倍の割増賃金を支給する
労働基準法改正により、企業は従業員の月60時間超の残業に対して、基礎賃金に加え50%以上の割増賃金を支払わなければならなくなりました。以下では、月60時間超の残業や休日・深夜の割増賃金について説明します。
-
(1)月60時間超の残業には50%の割増賃金率が適用
労働基準法では、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて労働者が残業(法定外残業)をした場合、企業に対して通常の賃金だけではなく、割増賃金の支払いを義務づけています。
これは、企業に対して経済的負担を課すことで、時間外労働を抑止し、長時間労働による労働者の負担を軽減することを目的とした、政府の働き方改革の一環です。実務上よく「残業手当」と呼ばれるこの割増賃金は、労働者の適正な賃金確保のため、重要な制度となっています。
割増賃金率は、残業時間の種類によって異なります。そのひとつが月60時間超の残業に対して適用される50%の割増賃金率です。企業は、労働者が月60時間を超えて働いた場合、60時間を超えた時間に対しては、50%の割増賃金を支払わなければなりません。
なお、月60時間超の残業に対する50%の割増賃金率は、正社員だけでなく契約社員やアルバイト・パートなどすべての労働者が含まれます。 -
(2)月60時間超の残業以外にもさまざまな割増賃金率がある
労働基準法では、月60時間超の残業のほかにも、以下のような場合に割増賃金の支払いが必要と定められており、それぞれ割増賃金率が異なります。
割増賃金の発生条件 割増賃金率 時間外労働* 月60時間まで 25% 月60時間超 50% 深夜労働 午後10時~翌午前5時まで 25% 休日労働 法定休日(深夜労働でない時間) 35% 時間外労働+深夜労働 時間外労働が月60時間まで 50%
(25%+25%)時間外労働が月60時間超 75%
(50%+25%)休日労働+深夜労働 法定休日の午後10時~翌午前5時まで 60%
(35%+25%)
労働時間の種類に応じて適用される割増賃金率が異なるため、残業代計算にあたっては、しっかりと区別して計算していくことが大切です。
*時間外労働とは、1日8時間・週40時間のいずれかを超えての労働です(労働基準法第32条)。所定時間を超えていても1日8時間・週40時間以内の労働は法内残業となり割増賃金の対象とはなりません。なお、保健衛生業及び接客娯楽業のうち、常時労働者が10人未満の事業では、1日8時間・週44時間の特例が定められています(労働基準法規則第25条の2第1項)。
2、令和5年4月から中小企業も月60時間超の割増賃金率の対象に
月60時間超の残業に対する50%以上の割増賃金は、大企業と中小企業とで適用された時期が異なります。現在では、すべての企業に対して、50%以上の割増賃金率が適用されていますが、そこに至る経緯をみていきましょう。
-
(1)大企業は平成22年4月から月60時間超の割増賃金率が適用
長時間労働を抑止し、労働者の生活と健康を守る目的で、平成22年4月に改正労働基準法が施行されました。
改正法労働基準法では、以下の「資本金の額または出資の総額」または「常時使用する労働者の数」のいずれも満たさない大企業に対してのみ、月60時間超の残業に対する50%以上の割増賃金率が適用されていました。
【中小企業の条件】業種 資本金の額または出資の総額 常時使用する労働者の数 小売業 5000万円以下 50人以下 サービス業 5000万円以下 100人以下 卸売業 1億円以下 100人以下 その他 3億円以下 300人以下 -
(2)中小企業は令和5年4月から月60時間超の割増賃金率が適用
平成22年4月施行の改正労働基準法では、中小企業に対しては、月60時間超の残業に対する50%の割増賃金率の適用が猶予されていました。これは、中小企業が業務体制の見直しや人件費削減のための設備投資をするためには、一定の時間と費用がかかることに配慮した措置になります。
しかし、そのような猶予措置は令和5年3月末で終了し、同年4月1日からは、中小企業に対しても月60時間超の割増賃金率が適用されることになりました。
その結果、現在ではすべての企業に対して、月60時間超の残業に対する50%の割増賃金率が適用されています。
3、計算例モデルケース
労働者が月60時間を超える残業をした場合、企業はどの程度の残業代を負担しなければならないのでしょうか。以下では、3つのモデルケースを挙げて、残業代の計算方法を説明します。
-
(1)月60時間超の割増賃金の計算例
【モデルケース①】
- 月給25万円
- 所定労働時間が1日8時間(午前9時から午後6時、休憩1時間)
- 年間休日120日
- ある月の時間外労働が80時間
残業代の計算は、以下のような計算式に基づいて行います。
1時間あたりの基礎賃金 × 割増賃金率 × 残業時間
月給制の場合、1時間あたりの基礎賃金は、以下のように計算します。
1時間あたりの基礎賃金 = 月給 ÷ 1か月の平均所定労働時間
1か月の平均所定労働時間 = (365日 - 1年間の所定休日日数) × 1日の所定労働時間÷12か月
・1時間あたりの基礎賃金
モデルケースにおける1時間あたりの基礎賃金は、以下のようになります。
月給25万円 ÷{(365日 - 120日) × 8時間 ÷ 12か月} ≒ 1531円(1時間あたりの基礎賃金)
次に、実際の残業代を計算してみましょう。
残業代は月60時間までの部分と月60時間を超える部分で割増賃金率が異なるため、ある月の残業時間80時間について、それぞれ分けて計算しなくてはなりません。
・時間外労働(月60時間以内)
時間数:60時間
割増率:25%(1.25倍)
計算:基礎賃金1531円 × 1.25 × 60時間 = 11万4825円
・時間外労働(月60時間超)
時間数:20時間(80時間 - 60時間)
割増率:50%(1.5倍)
計算:基礎賃金1531円 × 1.5 × 20時間 = 4万5930円
・合計残業代:16万0755円
(11万4825円 + 4万5930円)
すなわち、モデルケース①における残業代の総額は、16万0755円となります。 -
(2)月60時間超と深夜労働が重なった場合の割増賃金の計算例
【モデルケース②】
- 月給25万円
- 所定労働時間が1日8時間(午前9時から午後6時、休憩1時間)
- 年間休日120日
- ある月の割増賃金の対象となる労働時間の内訳:時間外労働が80時間、そのうち15時間は深夜労働と重複(深夜労働のうち5時間は月60時間以内の時間外労働、10時間は月60時間超の時間外労働)
モデルケース②における1時間あたりの基礎賃金は、モデルケース①と同様に
25万円÷{(365日-120日)×8時間÷12か月}≒1531円
になります。
モデルケース②では、時間外労働と深夜残業が重複しているため、以下のように計算をします。
・時間外労働(月60時間以内、深夜労働との重複分を除く)
時間数:55時間(60時間 - 5時間)
割増率:25%(1.25倍)
計算:基礎賃金1531円 × 1.25 × 55時間 = 10万5256.25円
・時間外労働(月60時間超、深夜労働との重複分を除く)
時間数:10時間(80時間 - 60時間 - 10時間)
割増率:50%(1.5倍)
計算:基礎賃金1531円 × 1.5 × 10時間 = 2万2965円
・深夜労働+時間外労働(月60時間以内)の重複分
時間数:5時間
割増率:50%(深夜25% + 時間外25% = 50%(1.5倍))
計算:基礎賃金1531円 × 1.5 × 5時間 = 1万1482.5円
・深夜労働+時間外労働(月60時間超)の重複分
時間数:10時間
割増率:75%(深夜25% + 時間外50% = 75%(1.75倍))
計算:基礎賃金1531円 × 1.75 × 10時間 = 2万6792.5円
・合計残業代:16万6496.25円
(10万5256.25円 + 2万2965円 + 1万1482.5円 + 2万6792.5円)
小数点以下の計算は原則として1か月単位で計算し四捨五入します。この場合、時間外労働の0.5円については四捨五入して繰り上げます。
すなわち、モデルケース②における残業代の総額は、16万6496円となります。 -
(3)月60時間超と休日労働が重なった場合の割増賃金の計算例
【モデルケース③】
- 月給25万円
- 所定労働時間が1日8時間(午前9時から午後6時、休憩1時間)
- 年間休日120日
- ある月の割増賃金の対象となる労働時間の内訳:時間外労働が80時間、そのうち法定休日労働が8時間
モデルケース③における1時間あたりの基礎賃金は、モデルケース①と同様に
25万円÷{(365日-120日)×8時間÷12か月}≒1531円
になります。
モデルケース③では、時間外労働と法定休日労働をそれぞれ分けて計算しなくてはなりません。
・時間外労働(月60時間以内)
時間数:60時間
割増率:25%(1.25倍)
計算:基礎賃金1531円 × 1.25 × 60時間 = 11万4825円
・時間外労働(月60時間超)
時間数:12時間(80時間 - 60時間- 8時間)
割増率:50%(1.5倍)
計算:基礎賃金1531円 × 1.5 × 12時間 = 2万7558円
・法定休日労働
時間数:8時間
割増率:35%(1.35倍)
計算:基礎賃金1531円 × 1.35 × 8時間 = 1万6534.8円
合計残業代:15万8917.8円
(11万4825円 + 2万7558円 + 1万6534.8円)
小数点以下の計算は原則として1か月単位で計算し四捨五入します。この場合、休日労働の0.2円については四捨五入して切り捨てます。
すなわち、モデルケース③における残業代の総額は、15万8918円となります。
4、社内体制の整備・相談は弁護士へ
残業代の未払いを防止するための社内体制の整備や労働者から残業代請求に対する対応は、専門家である弁護士にお任せください。
-
(1)割増賃金率引き上げに伴う社内体制の整備をサポートできる
月60時間を超える残業に対する50%の割増賃金の猶予措置が終了し、現在では、中小企業に対しても大企業と同様に割増賃金の規制が適用されます。
長時間の残業が常態化している企業では、月60時間を超える残業が発生している可能性があるため、多額の残業代の支払いが必要となります。人件費の削減は、企業の大きな課題です。よって、割増賃金率の引き上げに対しては、企業として以下のような対応が必要になります。- 労働時間の適正な把握
- 固定残業代の導入
- 残業の許可制の導入
- 業務効率化による労働時間の削減
具体的な対策は、企業の実情に応じて異なりますので、まずは弁護士に相談をして、最適な社内体制の整備に向けたサポートをしてもらうとよいでしょう。
-
(2)未払い残業代のトラブルを未然に予防するなら顧問弁護士の利用がおすすめ
未払い残業代のトラブルを未然に予防するには、普段から継続的に法律の専門家である弁護士のアドバイスやサポートを受けることが有効です。そのためには、顧問弁護士の利用がおすすめです。
顧問弁護士を利用すれば、いつでも気軽に相談ができ、労務管理に関する問題点の指摘や改善点の提案などがもらえるため、顧問弁護士のアドバイスに従って、対応することで未払い残業代のトラブルを未然に防ぐことができます。
弁護士というとトラブルが発生してから依頼するものと考える方もいますが、トラブルを未然に防ぐ予防法務も弁護士の重要な役割です。 -
(3)労働審判や訴訟に発展したときの対応も任せられる
労働者に対する残業代の未払いがある場合、労働者から未払い残業代請求をされる可能性があります。
このような場合には、まずは交渉により解決を試みますが、労働者の提示する条件との間に大きな隔たりがあると、交渉が決裂し、労働審判や訴訟に発展するかもしれません。弁護士に依頼することで労働者との対応を一任することが可能です。もし労働審判や訴訟に発展したとしても安心して任せることができます。
5、まとめ
月60時間を超える残業をした労働者に対しては、基礎賃金の1.5倍以上の割増賃金の支払いをしなければなりません。割増賃金の支払いは労働基準法上の義務になるため、きちんと対応していく必要があります。
また、50%の割増率が適用されると残業代の金額も高額になってしまうため、人件費を削減するためには、労働時間の削減に向けた社内体制の整備が重要です。そのような社内体制の整備にあたっては、顧問弁護士のサポートが有効ですので、まだ顧問弁護士を利用してない企業は、積極的に利用に向けた検討を進めることをおすすめします。
労働問題に対応できる顧問弁護士をお探しの経営者の方は、ベリーベスト法律事務所 横浜オフィスまでお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています