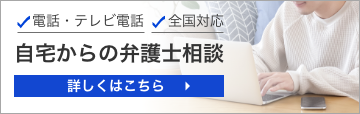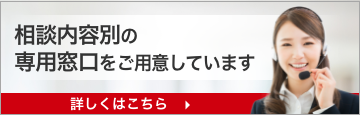正当な解雇理由と具体例|違法な解雇とならない条件や解雇の手順
- 労働問題
- 解雇理由
- 例
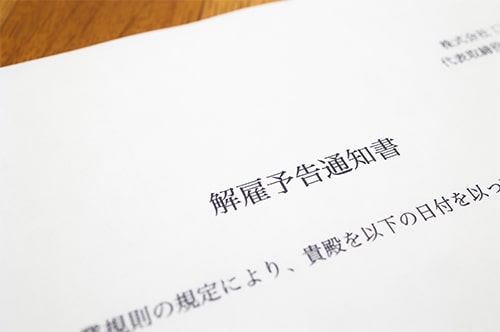
企業では、さまざまな理由から従業員の解雇を検討することがあります。
しかし、日本の法律では従業員の雇用が手厚く守られていますので、従業員を解雇するためには厳格な要件を満たさなければなりません。安易に従業員を解雇してしまうと、不当解雇を理由に従業員から訴えられるなどのリスクが生じてしまいます。
また解雇は、種類ごとに要件や解雇理由が異なりますので、状況に応じて慎重かつ適切な解雇の手段を選択していく必要があります。
今回は、不当解雇を回避するために解雇の種類ごとの正当な解雇理由と具体例、条件、手順などをベリーベスト法律事務所 横浜オフィスの弁護士が解説します。
1、正当な解雇理由と種類
会社が従業員を解雇する際には、正当な理由が必要になります。以下では、正当な解雇理由と解雇の種類について説明します。
-
(1)解雇には正当な理由が必要(労働契約法16条)
解雇は、会社側の一方的な意思表示により労働者との労働契約を終了させる処分になります。解雇された労働者は、生活していくために必要な収入源を失うという重大な不利益を被りますので、会社は自由に解雇をすることができず、厳格な要件を満たした場合にのみ解雇することができます。
労働契約法16条では、解雇の要件として以下の2つを挙げています。- ① 客観的に合理的な理由があること
- ② 社会通念上相当であること
このような要件を満たさない解雇は、不当解雇になる可能性がありますので、慎重に対応することが必要です。
-
(2)解雇の種類
解雇には、以下の3つの種類があります。
- ① 普通解雇
普通解雇とは、従業員による労働契約上の債務不履行を理由とする解雇です。一般的に「解雇」という場合、普通解雇を指すことが多いです。 - ② 懲戒解雇
懲戒解雇とは、従業員による企業秩序違反があった場合に制裁として科される懲戒処分の一種です。懲戒解雇は、懲戒処分の中でももっとも重い処分となります。 - ③ 整理解雇
整理解雇とは、企業の経営悪化を理由とした人員削減のために行われる解雇です。他の解雇は、従業員側に何らかの落ち度がありますが、整理解雇は会社側の一方的な都合によってなされるのが特徴です。一般的に「リストラ」という場合、整理解雇を指すことが多いです。
- ① 普通解雇
2、解雇の具体例|種類ごとに解説
以下では、解雇の種類ごとに解雇の要件と具体例を説明します。
-
(1)普通解雇の要件と具体例
会社が普通解雇をするためには、前述したとおり「客観的に合理的な理由があること」「社会通念上相当であること」の2つの要件を満たす必要があります。
つまり、従業員に解雇事由に相当する行為があり、解雇という処分を選択することが社会通念上相当であるといえなければなりません。
このような普通解雇が行われる具体的例としては、以下のとおりです。- 能力不足
- 私傷病による就労不能
- 勤労意欲や協調性の欠如
- 頻繁な遅刻や欠勤
- 業務命令違反
なお、従業員に解雇事由に該当する事情があったとしても、直ちに解雇することはできません。従業員に対して適切な指導・教育を行い、改善の機会を与えたにもかかわらず態度が改まらないような場合に普通解雇が可能になります。
-
(2)整理解雇の要件と具体例
整理解雇の要件は、法律上明記されているわけではありませんが、判例により、以下のような4つの要件(要素)に基づいて判断されます。
【整理解雇の要件】
- ① 人員整理の必要性:経営状況の悪化など企業経営上の必要性があること
- ② 解雇回避努力義務の履行:配置転換や希望退職者の募集など他の手段により解雇回避の努力をしたこと
- ③ 人員選定の合理性:整理解雇の対象者の選定が客観的・合理的な基準に基づいており、その運用も公正であること
- ④ 解雇手続きの妥当性:労働組合や労働者に対して、解雇の必要性・時期・規模・方法などの説明を行ったこと
整理解雇は、他の解雇とは異なり、会社側の一方的な都合により行われるものであり、従業員側には一切落ち度がありません。そのため、解雇の要件は、普通解雇および懲戒解雇よりも厳格に判断されることになります。
このような整理解雇が行われる具体例としては、以下のとおりです。- 経営の立て直しを目的とした人員整理を理由とする解雇
- 余剰人員の整理を目的とした解雇
- 不採算部門の閉鎖に伴う解雇
-
(3)懲戒解雇の要件と具体例
会社が懲戒解雇をするためには、解雇としての要件を定める労働契約法16条だけでなく、懲戒処分の要件を定める労働契約法15条の要件も満たす必要があります。
懲戒解雇の要件をわかりやすく示すと以下のようになります。- 懲戒事由が就業規則に定められていること
- 懲戒の種類として「懲戒解雇」が就業規則に定められていること
- 従業員が懲戒事由に該当する行為をしたこと
- 懲戒解雇という処分を選択するのが社会通念上相当であること
- 懲戒解雇をするまでの手続きが適正であること
懲戒解雇は、懲戒処分の中でももっとも重い処分になりますので、その有効性は、他の懲戒処分よりも厳格に判断されます。軽微な企業秩序違反だった場合、それに対して懲戒解雇をするのは不当解雇となる可能性もありますので注意が必要です。
このような懲戒解雇が行われる具体例としては、以下のとおりです。- 業務命令違反
- 業務上横領などの社内での犯罪行為
- 飲酒運転などの私生活における犯罪行為
- 重要な経歴詐称
- 長期の無断欠勤
- 悪質なハラスメント
3、不当解雇によって生じる問題やリスク
企業が正当な解雇理由がないにもかかわらず従業員を解雇してしまうと、不当解雇を原因として以下のような問題やリスクが生じるおそれがあります。
-
(1)従業員を復職させなければならない
正当な解雇理由がないにもかかわらず解雇をしてしまうと、不当解雇となり当該解雇は無効になってしまいます。つまり、当初から解雇としての効力が生じていないことになりますので、解雇した従業員を職場に復職させなければなりません。
また、不当解雇というトラブルが生じた従業員を復職させると、職場の雰囲気が悪化し、他の従業員のモチベーション低下につながるおそれがあります。 -
(2)解雇期間中の給与をさかのぼって支払う
従業員の解雇が無効になった場合、会社には解雇期間中の賃金を支払う義務があります。解雇期間中も従業員だったことになり、その間の給料は未払いとなっているはずです。
そのため、会社は、実際に従業員が働いていないにもかかわらず、解雇期間中の給料を支払わなければなりません。不当解雇の争いが長期化すると、数年分の給料をまとめて支払わなければならないこともありますので、会社の経済的な負担は非常に大きなものとなります。 -
(3)損害賠償や慰謝料を請求される
不当解雇された従業員が被った精神的な苦痛は、基本的には、解雇期間中の給与が支払われることによって償われると考えられています。そのため、不当解雇をしたからといって、常に従業員から慰謝料を請求されるわけではありません。
しかし、不当解雇に至る経緯に著しい違法性が認められる事案であれば、従業員から慰謝料請求をされるリスクもあります。
4、従業員を解雇する際の手順・流れ
従業員を解雇する際には、以下のような手順・流れで行います。
-
(1)解雇要件を満たすかどうかを検討する
従業員を解雇する場合、正当な解雇理由がなければ不当解雇となるリスクが生じます。そのため、まずは解雇の種類ごとに必要な解雇要件を満たしているかどうかを確認します。
解雇要件を満たすかどうかは、法的判断が必要になりますので、判断に迷うときは労働問題の解決実績がある弁護士に相談するようにしましょう。
また、悩むようであれば、解雇も手段として想定しつつ、退職勧奨によって問題解決を試みるのも一案です。 -
(2)解雇理由をまとめる
従業員に対して解雇を告げると、従業員から解雇理由をたずねられたり解雇理由証明書の交付を求められたりすることがあります。
その際に解雇理由をしっかりと説明できなければ、従業員から不当解雇を疑われ、訴えられてしまうリスクが生じます。そのため、従業員に十分説明できるだけの解雇理由をまとめておくようにしましょう。 -
(3)解雇予告を行う
会社が従業員を解雇する際には、少なくとも解雇日の30日前までに予告することが義務付けられています(労働基準法20条1項)。これを「解雇予告」といいます。
ただし、解雇予告期間に不足する日数分の平均賃金を支払うことで、解雇予告期間は短縮することが可能です。このような賃金を「解雇予告手当」といいます。
基本的には、30日前までの解雇予告により対応し、どうしても解雇予告期間を設けることができない場合には、解雇予告手当を支払うという対応をするとよいでしょう。 -
(4)解雇通知書を交付する
解雇予告を行ったら従業員に対して解雇通知書を交付します。
解雇通知書には、解雇の理由や解雇日、解雇予告手当の支払いに関する事項などを記載します。また、従業員が受領したことを明確にするために、人事や上司が立ち会ったり、受領書への署名・捺印を求めたりすることも大切です。
5、まとめ
従業員を解雇する際には、正当な解雇理由がなければ不当解雇であるとして従業員から訴えられてしまうリスクがあります。
解雇理由の正当性は、専門的な知識や経験がなければ正確な判断は困難といえます。そのため、解雇の判断に迷ったときは、早めに弁護士に相談するのがおすすめです。
従業員の解雇でお困りの人事・経営者の方は、まずはベリーベスト法律事務所 横浜オフィスまでお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています