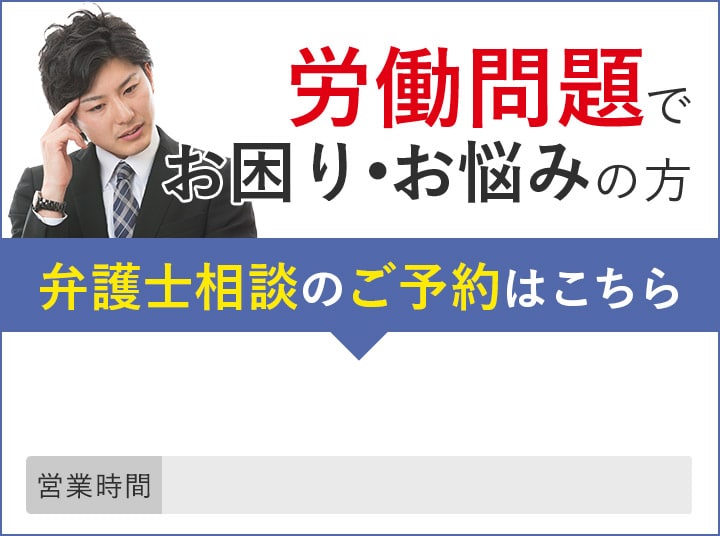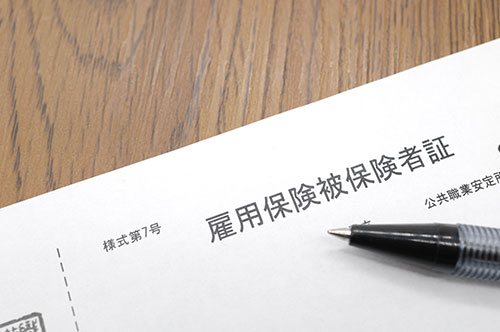二重就業でアルバイトはばれたらNG? 労働者向け副業・兼業の注意点
- 労働問題全般
- 二重就業

収入アップやスキルアップのために副業や兼業に興味を持つ方は多いでしょう。しかし、就業規則で「二重就業(二重雇用)」が禁止されている会社にお勤めされている場合、実際に発覚したら解雇や懲戒処分となるかもしれないと不安を持たれているかもしれません。
本コラムでは、法律上における二重就業の位置づけから、就業規則が持つ拘束力について、労働問題についての知見が豊富なベリーベスト法律事務所 横浜オフィスの弁護士が解説します。


1、二重雇用(副業・兼業)とは
-
(1)二重就業の定義と概要
二重就業(副業・兼業)は、本業とは別の仕事に従事することをいいます。
たとえば、サラリーマンとして勤めながら週末は清掃作業のアルバイトをする、販売員の正社員をしながら休日は個人事業主として手作り雑貨を作って売るなどです。
なお、副業に似た言葉に兼業があり、一般には本業とほぼ同じ時間や労力をかけている仕事を兼業、スキマ時間で稼ぐ仕事を副業と分けられることがあります。ただし、副業と兼業が法律によって明確に分けられているわけではなく、同じ意味で使われていることもあるので、この記事では「二重就業=副業・兼業・アルバイト」とします。 -
(2)副業や兼業への関心が広まる理由
二重就業者が増えている背景のひとつには、現代人の長寿化が進み、人生100年時代と呼ばれる時代が到来していることがあげられるでしょう。
厚生労働省が公開している「副業・兼業の促進に関するガイドライン」では、人生100年時代では若いときから自分の希望する働き方を選べる環境を作ることが必要とされています。これは、一企業にとらわれず能力を発揮したい、スキルアップしたい、という労働者をバックアップするために、二重就業の環境を整備することが重要であることを示しています。
また同様に、みずほ総合研究所でも、人生100年時代といわれながら長く企業に勤めているだけでは生き抜くのが難しいという状況があり、キャリアの二毛作(あるいは多毛作)の必要性が高まっているとしています。
実際、同研究所のアンケート結果で明らかになった二重就業を希望する理由は、収入を増やすため、というものだけではありません。自分が活躍できる場を広げたいから、さまざまな分野における人脈を構築したいからなど、スキルアップや今後のキャリアに関する理由もあがっています。
このような二重就業を希望する声は、今後ますます大きくなることは想像に難くないでしょう。企業としても、二重就業についてどうするべきか、真剣に考えなければいけない局面を迎えているといえます。
2、二重就業のメリットとデメリット
-
(1)二重就業のメリット
二重就業のメリットのひとつは、ご自身のスキルアップが期待できる点です。たとえ同じ職種であっても、他の企業の仕事に従事することで、視野の拡大や能力開発が見込めます。実際に従事している業務を通じて新しいアイデアや広げることもでき、自分自身のキャリア形成や将来の選択肢を増やす可能性もあるでしょう。
また、限られた労働時間の中でいかに成果を出すことができるか自然に考えるようになり、生産性が向上することも期待できます。ふたつの仕事をこなしていくためには、自身による労働時間や健康の管理が欠かせないからです。
ほかにも、給与に対する不満が落ち着く可能性があることも、二重就業を行い副業やアルバイトを行うことのメリットといえるでしょう。 -
(2)二重就業のデメリット
二重就業を行い、本来の業務のほかにアルバイトや副業を行う最大のデメリットは、自身の労働時間や健康管理が難しくなる点です。
会社が二重就業に懸念を示す理由としては、従業員の業務パフォーマンスへの影響を心配している場合があります。このような会社の懸念を理解した上で、本業に支障が出ないよう自己管理することが重要です。さらに、会社側としては、業種によっては情報漏えいなど自社に損害が発生するリスクが高くなると考えるケースが少なからずあります。
そのため、副業禁止を明言する会社が存在しますし、就業規則で定められているケースもあります。副業や兼業をしたいとお考えであるならば、まずは自己管理を求められることは間違いないでしょう。さらに、ご自身の権利を守るためにも、就業規則も目を通しておくべきといえます。
3、副業禁止は絶対? 就業規則の拘束力
-
(1)就業規則の拘束力が有効とみなされるケースとそうでないケース
二重就業(副業や兼業、本業のほかのアルバイト)そのものは、法律で禁止されていません。そのため、会社に許可されている場合はもちろん、禁止されている場合においても、就業規則で適切なルールを定められている必要があります。
まず労働基準法の基本的な考え方として、休日および休憩時間は使用者の支配が及ばず、労働者は自由であるとされています。したがって、就業規則ですべての二重就業を禁止にするのは難しいとするのが一般的な考え方です。
過去の判例でも、就業規則で二重就業を禁止していても、副業をした労働者を直ちに解雇や懲戒処分するのは無効、とみなされることが少なくありません。
一方で、企業が二重就業を就業規則で規制する理由には、労働者の健康維持や疲労回復、情報漏えいのリスクを回避するという意味が含まれていて、一定の合理性があると解釈されることもあります。
そのため、二重就業によって欠勤や遅刻が著しく増加した、会社に実損が生じる可能性が高い、などのケースであれば、就業規則による規制が有効となる可能性が高いでしょう。さらに、実際に会社の利益に影響が出たり社会的信用が低下したことが明らかな場合は、解雇されてしまう可能性もあります。法的に規制がないからといって、どのような副業・兼業・アルバイトを行ってもいいという意味ではないことに注意が必要です。 -
(2)二重就業に関する裁判例
就業規則の拘束力は、そこに合理性があるかどうかが焦点になります。
過去の裁判でも、運送会社の準社員がアルバイトの許可を求めたものの、会社が4度にわたって許可を認めなかった事件では、うち2回の不許可に合理的な理由がないことから、会社に対して慰謝料の支払いが命じられました(京都地判平成24年7月13日)。
また、二重就業をしていた私立大学の教授に対して懲戒解雇が下されたものの、本業への支障が認められないことなどから解雇が無効とされた事例もあります(東京地判平成20年12月5日)。
一方で、二重就業を許可なく行っていた建設会社の社員を解雇した事件では、副業が深夜に及ぶもので本業に支障をきたす可能性が高いことなどから有効とみなされました(東京地決昭和57年11月19日)。
お問い合わせください。
4、副業や兼業を行うときの注意点
-
(1)就業規則をしっかり確認する
不要なトラブルになる事態を避けるためにも、副業や兼業を始めるときは、まずは就業規則をしっかり確認してください。
就業規則に以下のような項目がある場合は、適切に対応しておくことをおすすめします。- 二重就業を希望する労働者は事前に会社に届け出(副業の内容、勤務時間、業務量など)をする
- 本業に影響が出る、情報漏えいにつながる、会社の名誉を損なう、使用者と競合するような業務を行うなどの場合は、禁止または制限する
-
(2)二重就業が発覚して問題になったらすべきこと
もしすでに二重就業(副業・兼業)をしていて、会社に発覚した場合は、会社側から、副業の内容、勤務時間、業務量などについてヒアリングされるかもしれません。その場合は、素直に応じるほうがよいでしょう。
万が一、二重就業を理由に解雇や懲戒処分が下されてしまったら、速やかに弁護士への相談を検討してください。労働問題の解決実績が豊富な弁護士に相談すれば、状況を確認した上で、どうすれば円満に解決できるのかアドバイスを受けることが可能です。
労働基準監督署(労基署)などへの相談もできますが、たとえ依頼しても個別に交渉したり対応してくれたりすることはできません。弁護士に対応を依頼すれば、会社との交渉から任せることが可能です。訴訟を視野に入れた対応ができるため、会社側も強固な姿勢を維持することが難しくなるケースがほとんどです。
5、まとめ
副業や兼業、アルバイトなどの二重就業は現代の多様な働き方のひとつとして定着しつつありますが、労働者が知っておくべき法的課題も少なくありません。本コラムで解説したように、労働時間の通算義務や残業代計算の問題、就業規則による制限の有効性など、複雑な法的側面があります。
副業・兼業を検討している方は、まず就業規則を確認し、必要に応じて会社と誠実に協議することが大切です。また、トラブルが生じた場合や権利が侵害されていると感じる場合は、早い段階で労働問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。ベリーベスト法律事務所 横浜オフィスでは、労働問題についての知見が豊富な弁護士がアドバイスを行います。二重就業を行っていることで、会社から不当な処分を受けたり、解雇されそうなときはお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
- |<
- 前
- 次
- >|